姿勢を正す理由とは
2025年8月19日
 暑すぎる夏でも仕事や勉強は待ってくれない。
暑すぎる夏でも仕事や勉強は待ってくれない。
集中力を高めたいと思いませんか。
弊社のある取引先の企業では、会議や研修のはじめに
「姿勢を正してください」
と担当の社員が号令をかけます。
それを合図に社員全員が「はい!」と背筋を伸ばして返事、
「宜しくお願いします」と大きな声で挨拶をしています。
この企業では、全国どの支店に行ってもこの習慣が徹底されています。
当初、私は号令をかけてする挨拶になじめず、挨拶は強制するものではない、などと違和感を感じていました。
しかし、伺うことが長くなって、最近では私も「姿勢を正してください」という号令がないと物足りない。
「号令をお願いします」と催促している自分を発見しています。
なぜでしょう。
背筋をピンと伸ばすと、私も気持ちのモードが切り替わります。
「宜しくお願いします」とあいさつをされると、私は「講師」参加者は「教わる人」になり緊張が生まれます。
反対に、休憩でその境界がなくなるとざっくばらんな関係性が生まれます。
そういえば「無礼講」というのは、立場を取り払って人と人になった状態ですよね。
考えてみれば、日本の習い事や芸事も武道も、皆、挨拶に始まり挨拶に終わります。
茶道のお稽古でもお稽古の始まりと終わりに、扇子で境界を示し背筋を伸ばして挨拶をします。
日常でもご飯を食べるときは「いただきます」。食事が終わったら「ご馳走様」
日本人はひとつひとつの行動に境界を設けているようです。
さて、この姿勢を正す姿勢が、実は、集中を高めるには効果的だそうです。
例えば、かるた取りの名人の粂原圭太郎氏によるとかるたの競技では
「姿勢を正すことで、視線・手元・思考のベクトルが一致し、今やるべきことに集中できるようになる」そうです。
姿勢を正す習慣そのものが脳のトレーニングになり。意志力と集中力を同時に底上げしてくれるようです。
ではその集中力を切らさないたいめにはどうしたらよいのでしょう。
かるた名人はどうしてもさまざまな感情や雑念や生まれてしまうので、いかに素早く自分を取り戻すか、
そのために休憩時間は呼吸に集中し体を動かし深呼吸をする、そうです。
彼は、日頃から瞑想をしているので試合の休憩時にもすぐに自分を取り戻せるそうです。
棋士の羽生善治氏も、長い対局の中で集中力を発揮するためには「頭の中に空白の時間を作る」そうです。
頭のなかに空いたスペースがないと集中ができない。
だから、タイトル戦の前などはいったんそこから離れてぼーっとした時間を持つ、そうすると脳にスペースが生まれて集中力が高まるそうです。
ここぞというときには、きちんと姿勢を正す、そして時には手を止めて深呼吸する、ぼーっと遠くを眺める。
結構簡単な取り入れやすい習慣です。
やってみる価値はありそうです。
(YK)
参考図書:『ちはやぶる』と学ぶかるた名人の集中力 粂原圭太郎著
『決断力』 羽生善治著
関連セミナー
↓
女性がしなやかに働くための「ZEN式思考」 ~本質に気付き、自分らしく働く軸をつくる~
タグ :マインドフルネスを体験したい姿勢を正してください瞑想する集中力をきらさない方法
禅式思考とストレングスファインダー
2025年7月18日

私の周囲には(というとコーチングや人材育成関連の方々なのですが)「禅」を勉強し得度した人や「禅」を実践している人が多くいます。
デジタル社会に疲れた人たちに「必要な習慣」として「禅」や「マインドフルネス」がもうずいぶん前から注目されています。
多くのタスクやミッションに追われる人たちにとって「手放すこと」「執着を捨てること」を意識することが大切であり、禅式思考が効果的だと言われています。
手放せは新たなものが入ってくる。
特に日々、時間に追われて働いている女性には取り入れたい思考法かも知れません。
一方、「執着」することはマイナスなのだろうか、とも実はずっと考えています。
執着する気持ちがあるからこそ、生きる活力が生まれるのではないだろうか。
そもそも子供の頃教わったことは、簡単にあきらめないこと、継続すること、だったはずと思うのです。
一概に「昭和的」と言っていいのでしょうか。
もう少し単純な例でいくと、物を整理する断捨離が良いとする風潮。
確かに、すっきりした部屋でシンプルに暮らせば、面倒くさくないし心も軽くなりそうです。
でも、これも日本人は物を大切にするのが美徳、と言われていたのではないか。
捨てることを奨励するって、そしてそれを転売するって、その手間こそ私にとっては面倒です。
そんな折、知人のコーチからストレングスファインダーというギャロップ社の診断ツールを使ったコーチングを受けました。
この診断では、強味を34個に分類して示し、強味のトップ10を教えてくれます。
そしてそのTOP10の私の強みの一つに「収集心」があるのを知りました。
「好奇心を持ち、情報、アイデア、芸術品、人間関係も含めて収集し保管する」
確かに私は一度始めたことはやめない、あきらめない。
実を結ばなくても、使っていなくても、捨てるのが苦手です。
知人はコーチングのなかで
「様々な収集を行っているからこそ信頼性の高い情報に基づく判断を下したり
アウトプットをすることが出来る!」
収集することは私の強みだった!
コーチに認めてもらい心が楽になりました。
断捨離できず増え続ける書籍や印刷物、アルバムの数々、
腹をたてても縁を切らない人間関係、
私にとって捨てられないのは、それも含めて未来へつながるものだと気づいて腹落ちしました。
一方、ここ数年、私がやっていて気持ちの落ち着く時間が3つほどあります。
その一つが書道。
もう20年以上、字の上達が目的ではなく、また展覧会に出すことをするわけでもなく、
ただひたすら経文(般若心境だけではなく)や石碑に残された古人の隷書、草書、楷書などの写しをお手本に毎月数枚を仕上げています。
賞を目指すわけでもなく、誰かに見せるわけでもなく、それでも長く続いている理由、
それは、上手になりたいという「欲」がない、ただ書くことが楽しい、だから継続しているのだと最近気づきました。
まさにこれは禅的。
もしかすると企業のおいても、意味のないことを一生懸命やる時間、を取り入れるのも良いのかも知れません。
かつての日本の会社や学校では、掃除をする時間、がそれであったのかも知れません。
さて、私はさらに、茶道のお稽古、禅リトリートと全て気づけば禅的活動が増えています。
そしてそれらを手放すどころか活動を「収集」継続しています。
執着を捨てようとして始めたことに執着して、ますます忙しくなる、
しかし終わった後の爽快感は、スポーツにも似ています。
これも人間らしいことなのかなと納得しています。
禅の視点を取り入れたセミナーを開始します。是非一度、ご参加ください。
(YK)
タグ :ストレングスファインダー女性管理職の課題手放す断捨離出来ない禅禅リトリート
女性の話が一言で終わらないわけ
2025年4月11日
 先日、男性の知人に聞かれました。
先日、男性の知人に聞かれました。
奥さんに「今日何時に帰るの?」と尋ねると時間を聞いているのに、
どこへ行って何をしてだから何時になると細かく答えてくれる。
時間を聞いているだけなのに、どうして行動を説明するのだろうと思うそうです。
確かに、女性は聞かれたことだけに答えずに前段後段と
話を長くする人は多いように思います。
私の推察ですがその方の奥様は
①ご主人に外出するいきさつについて話を聴いて欲しかった
②早く帰って欲しいと思っているのかなと深読みをして、理由をわかって欲しい。
③自分の外出の正当性を主張したい
というような要素があるのではないかと答えました。
というと、とても保守的なご夫婦の会話のようです。
「それは昭和の女性の話でしょう」と思われる方もいるかも知れません。
しかし、別にパートナー同士でなくても上司と部下、友人同士であっても
令和の時代であってもこういう会話はそこかしこにあるように思います。
例えば会議で意見を求められたときに、意見の背景にあるその個人的な状況を
長々と説明してくれる女性も同じような状況ではないでしょうか。
私もよく研修で、参加目的を聞いているのに自分の組織の問題や個人的な課題まで
長々説明してくれる女性に出会います。
女性の話は長いのです。
しかし、それは相手に配慮して、一方的になりたくないと思う女性の優しさからだと私は思っています。
相手にわかって欲しい、気持ちを共有したい。
その結果、女性の話は長くなります。
女性と男性の特性の違いについて話すと、それは日本人の女性の話でしょう、
と言われることがあります。
しかし、先日、グローバルな外国人が集まる会議に参加してやはり女性の話は長い、
そして開示が多いということを実感する機会を得ました。
ランチタイムに1時間前に初めて会ったばかりの女性が
私の私生活についての質問をズバリしてくる。
そしてそれは私に興味があるわけではなく、実は自分のことを話したいからなのです。
3泊4日の間に、「離婚をして子供を育てる不安を抱える女性」
「再婚の夫の息子を育て上げてこれから仕事を頑張りたい女性」
などなどの悩みを聞くことになりました。
そして直接聞いていなくても他の人が教えてくれるので、
20数名の参加者について情報共有がされました。(笑)
表面ではビジネスライクであるけれど、実はプライベートな事情は共有されていると
かなり親密な関係性が築かれていく。
むしろ日本の方がプライバシーには敏感で、一緒に働く人たちとの間では
こうしたプライベートな共有は避けられどんどん少なくなっている気がします。
女性の話が長いのは、古来から女性が自分と家族の身の安全性を保つため、
周囲との良い関係を築くコミュニケーション力にたけているからだとも言われます。
今のような世界の各地で互いのエゴがぶつかる時代、
個人的な打ち明け話がたくさん必要な気もします。
(YK)
https://www.businesscoach.co.jp/seminar/s190823-coaching-communicatinon.html
タグ :プライバシーとコミュニケーション女性の活躍を阻む12の習慣女性の特性女性の話は長いのか開示する
勝ちたがるクセありませんか?
2025年2月7日
 相手に共感したり承認したりすることが大切であることは、多くの方が知っているでしょう。
相手に共感したり承認したりすることが大切であることは、多くの方が知っているでしょう。
でも、日々、皆さんの周囲にはこのような会話がありませんか。
「喉が痛いときには、ハチミツを舐めるといいみたいよ」と言われて
「ああ、知ってる。毎日舐めてる」と答えた。
別にそれだけの会話ですが、教えてくれた相手を少しがっかりさせたかも知れません。
何故なら、相手は知識をひけらかしたかったのではなく、心配して言ってくれているからです。
友人同士であればまだ良いけれど、仕事で部下や後輩からの提案にそう答えていたら
「もう二度と教えてあげない!」と相手は思うかも知れませんね。
「極度の負けず嫌い」
コーチングの権威マーシャル・ゴールドスミス博士は名付けています。
何を犠牲にしても、どんな状況でも、まったく重要でない場合でも勝ちたいと思う気持ち。
負けたくない。
この場合、ささいなアドバイスを知らない、さらに「知っているということを誇示したい。
些細なエゴです。
そこをぐっと押さえて会話の間に一言いれるとかなり異なった印象になるはずです。
「ありがとう。そうなのね」
自分が既に知っているかどうかは、言わなくてもいいのです。
何故ならこの会話で大切なのは、あなたが相手の心配してくれる気持ちを受け取ることのほうが大切だからです。
「今週末、トレッキングに行く予定なの」と言ったら
「ああ、私は興味ない」と答えられた。
自分のうきうきした気持ちや楽しみをちょっと共有したかったのであって、相手を誘っているわけではないし、興味を聞いているわけでもなかったのに、この返答では白けてしまいます。
なんだか自分の楽しみをけなされた気がします。
「わあ、素敵ね。晴れるといいね」でもいいですし
「どこへ行くの」と興味を示してあげれば相手は、自分の気持ちに共感してくれたと満足なのです。
単純なことなのに、誰にでも「自分は知っている」「自分は相手に迎合したくない」というエゴがあります。
相手の言葉を素直に受け取らない、同意しない。
昨今、多様性は重んじるということが重要視されています。
自分とは異なる人の気持ちを承認する社会が多様性のある社会です。
自分は違う意見や考えを持っていても、まず相手の発言は受けとめることは大切です。
難しいと感じる方は、ただ相手の言葉を繰り返してみてください。
「はちみつがいいのね」
「トレッキングへ行くのね」
それだけで相手は聞いてもらえたことで安心します。
あなたが知っているかどうか、興味があるかどうかはここでは関係ないのです。
是非、相手のつぶやきに自分の良し悪しを押し付けないように、頭の片隅に置いておいてください。
(YK)
参考「コーチングの神様が教える「できる人」の法則」 マーシャル・ゴールドスミス著(日経ビジネス人文庫)
タグ :コーチングの神様が教えるできる人の法則できる人の悪癖共感の会話良好な人間関係を築く会話のコツ
自信は自己評価
2024年11月1日

狸は化ける
「私、(手術を)失敗しないので」
と言い切る女医を主人公としたドラマが流行りました。
なぜ人気が出たのか、なぜなら多くの人が「失敗しない」と
言い切る自信を持ちたいものの、なかなか持てないからではないでしょうか。
中々、自信を見せるのは勇気がいります。
失敗したらどうしよう、
図々しいと嫌われないだろうか、
自分の実力を信じないとなかなか言えない言葉です。
でも「自信がある」と見せるか見せないかでは、仕事に重要な影響を与えます。
「自信がある」と断言すると、自信過剰だと思われるかもしれない。
でも「自信がない」と言うと、他人は不安になります。
実は、自信は自己評価です。
自分が感じとっている状態です。
自信=実力ではありません。
自信があるからといって実力があるとは限らない。
でも、「自信がある」ように見える人は、他人からは実力があるように見えます。
実力があるのに「自信がない」という人は、実力がないように見えてしまいます。
そして「自信がある」人に人は仕事を任せたいのは明らかです。
しかし、実力があるのに「自信がない」というのは悪いことばかりではありません。
なぜなら、謙虚な人だと人間性を評価されるからです。
最近の日本の男女の意識はかなり小さくなったとはいえ、国連からあれこれ指摘されるレベルがいまだに続いています。
若い世代の意識に関わらず、かなりマッチョな組織文化がいまだに多くの日本の組織にあるのが現状です。
それが「自信」とどのような関係があるのかというと、「男性は強くあるべきだ」というバイアスが
男性に「自信がありません」と言いにくくさせてはないでしょうか。
一方、女性は「私、自信があります」とは言いにくい。
謙虚さが美徳の傾向がビジネスの上でも相変わらずあるからです。
結果、実力はなくても声の大きい男性が昇進し、実力があるのにいつまでもアシスタントの女性が出来てしまいます。
実力とは別の話で経験がないから「自信がない」という人もいます。
しかし、人生は日々初めてのことだらけです。
過去に経験したことを応用して生きていると言っても
過言ではない気がします。
自分の応用力を信じてもいいのではないでしょうか。
期待をかけられたら、自信があるふりをしてみてください。
チャンスが来ないなら、自信があると宣伝しましょう。
SNSで自己演出しているように、仕事でも「出来る私」を演出しましょう。
自信を持つと経験が増えてくる、経験すると実力がついてくる、はず。
そして本当に実力がついてくると、謙遜しても他人には分かるようになるものです。
「私、失敗しないので」
言い切ってくれる人を、人は求めているような気がします。
自信を持つことは自分のためだけではないのです。
(YK)
関連セミナー↓
https://www.businesscoach.co.jp/seminar/s230302.htm
参考図書 「自信がないという価値」トマス・チャモロ=プリミュージック著(河出書房新社)
タグ :ドクターエックス出来るふりをする女性管理職が増えない理由自信がない自信と実力
違和感を覚えるとき~オーセンティック~
2024年10月11日
 違和感を覚えるとき。
違和感を覚えるとき。
地球の環境は大切だと常日頃口にしている人が
自分でオーダーした食事を残したとき。
本物志向と言っている人が
ブランドのコピーのバッグを持っているのを目にしたとき。
多様性を目指す会社のダイバーシティ推進室が女性だけで構成されている
と知ったとき。
社員は人材ではなく人財だ、と言っている企業の社長さんが
「一般社員とミーティングする暇はない」と言うとき。
「はて?」
違和感を覚えます。
それぞれに事情はあります。
私もしばしばやってしまっています。
「ダイエット中なのにデザートを食べてしまった」
「今日から英語の勉強をしようと思ったのにやらなかった」
というのであれば、これは自戒を込めた笑い話になります。
が、日頃、口にしている価値観や、
HPにうたっている企業の理念やビジョンと異なる行動をしている
言行不一致。
本人が気が付かないでやっている様子を見たときの違和感は、信頼への致命傷になります。
この違和感を覚えたとき
企業であれば消費者はそっと離れていくかも知れません。
政治家は批判され、判断されます。
しかし、残念なことに、個人については他人は指摘してくれません。
そして本人はどこまでも気が付かない、、、
オーセンティックリーダーという言葉があります。
Authentic.
本物であること。
オーセンティックリーダーとは、
自分を偽らない、どこまでも自分のままであるリーダー。
「自分らしくある」というのは
「素の自分」「飾らない自分」「自分が心地よい自分」を通すことではありません。
「どこまでも、どんなときでも自分の価値観に忠実である発言と行動をする」
リーダーです。
このオーセンティックリーダーというリーダーシップについて
最近の政治家たちの動きを見て、ようやく理解することができました。
あくまでも自分の信念に忠実な言動と行動を守ることは、組織の諸事情のなかで
生きている私たちには大変難しいことです。
が、そういうリーダーについていきたい、と人は思うのですね。
冒頭にあげた例も、本当に心からその人がそう考えているのであれば
方法はいくらでもあるはずです。
他人はそこを見ています。
価値観を守るということは、自分に厳しいことに他ならないと感じています。
(YK)
タグ :オーセンティックとははて?リーダーの言動言行一致
多数になると安心する
2024年7月22日
 このコラムでは男女差を随分扱ってきました。
このコラムでは男女差を随分扱ってきました。
が、この数年多様性に関する意識が進み、あまり違いを訴えるとそれこそが差別ではないか、
というご意見をいただくようになりました。
特に20代30代の方からに多い感想ですが、本当に男女差は世間では意識されなくなっているのでしょうか。
先日、知人の主催する一日リトリートに参加しました。
お寺で座禅をした後、相模湾を見下ろす大磯の山をトレッキングするのですがこの山道が半端なくきつい。
それでも自然の中で自分を見つめなおすには最高の機会なので、時々参加しています。
毎回7,8名の参加者で性は1,2名です。
今回は、現地に集合すると色とりどりの服装の女性が集まっています。
6名の参加者のうち女性が4名でした。
「わあ、良かった!」
最初の私の感想です。
今回は暑い日が続いていて熱中症アラートも前日は出されていたので、実は参加を相当ためらっていました。
体調がおかしいと感じたらリタイアしよう、
と一抹の不安を抱いていた私は女性が多数派であると知りほっとしました。
何故でしょう。
女性が多ければ、体力的には同じだから山を登るペースが遅くなる。
女性が多いと、トイレの休憩やリクエストを出しやすい。
彼女たちも同じように感じているに違いない。
単純な理由です。
案の定、女性二人が途中でショートカットをして頂上へ一足先に上り待つことを選び、
下りはタクシーを呼び、それでも最後にはふもとの古民家に集合し楽しい反省会となりました。
私は、予定どおり全ルートを完走。
山頂からの景色は感想した満足感で違って見えるし、山頂で食べるアイスクリームの味はさらに美味しい。
自分の体力に自信も付きました。
いつもは同行者に迷惑をかけないようにというプレッシャーがあったのが
「いつリタイアしてもいい。私だけではないのだから」という気持ちが安心感につながり
後押ししてくれた気がします。
また驚いたことに旧知の仲であっても男性たちと登るより、初対面の女性たちと登るほうが気が楽でした。
同性がいることが、心理的な安全をもたらせてくれたようです。
歩くスピードも女性に合わせ、水分補給も頻繁に行う、女性が多いからこそ女性の体力への配慮です。
さてトレッキングの人員構成で起きた変化は、組織についてもあてはまるのではないかと思います。
役員や管理職が集まる会議では多数派が男性という企業は、いまだに多いでしょう。
とすると、やはり、そこで意見を言うのは少数派の女性には難しいかも知れません。
今回のトレッキングで言えば「トイレに行きたい」と言いにくいのに等しい感じかも知れません(笑)
違いは緊張感をもたらします。
ある私の公開セミナーで、女性ばかりの参加者に男性がひとりということがありました。
その方は片隅に座り発言は少なく、終わるとさっと帰って行きました。
そもそも外見や自分とは異なる人の間に入って緊張感を感じるのは動物としての本能です。
良い悪いの問題ではなく、男性が女性ばかりの中に入っても同じことは起こります。
出来うる限り、メンバー構成にはバランスを取る、あらためて理にかなっていると思いました。
最近、男女共学の大学へ行ったときのこと、メイクアップをしている男子学生や全く性別不明の服装の女子学生が目につきました。
近い将来、外見でアウェイを感じることは、男女ともになくなる時代が来るのかも知れません。
それまではなんらかの配慮や工夫は必要でしょう。
異常に暑い夏、少なくとも体調管理については男性も女性も正しく自分で管理して主張しましょう。
(YK)
タグ :、心理的安全性ショートカットの勧めトレッキング男女のバランス登りきる人休む人
ジコチューと自己主張
2024年6月7日
 ジコチュー(自己中心)という言葉をとてもよく耳にします。
ジコチュー(自己中心)という言葉をとてもよく耳にします。
先週、某女子大のキャリア開発の講義に今年もゲストとして呼ばれて「ああはなりたくない大人」についてアンケートを取りました。
何故「ああはなりたくない大人」を尋ねるかというと、ビジョンや理想を聞いても答えが返らない人がほとんどだからです。
ビジョンを描く時代でもない、とも言われます。
だったら、逆を考えてもらおうというわけです。
多くの回答が集まりましたが、回答に多いのが、
・自分のことしか考えられない人
・全て自分中心の人
・協調性のない人
・ジコチューな人
全体的に「ジコチュー」を始めとする他人に迷惑をかけない、他人に嫌われる人にはなりたくないと思っているようです。
それは当然で良いことです。
女子大生に限らず、日本人は昔から「世間体」を気にします。他人の評価が道徳基準になりがちです。
皆に好かれたい、嫌な人と思われたくない。
大切なことです。
しかし、最近、モラハラだとかカスハラだとか日々耳にするにつれて、自分が加害者になってはしまわないかと、さらに発言に慎重になってしまう人も多いでしょう。
女性の多くがどのような働き方をしたいかと尋ねると「自分らしくいきいきと働きたい」という答えが多いことは毎回お伝えしています。
しかし、自分らしく、と思いながら他人の評価を気にしている、
となると自己矛盾してしまいます。
他人の思惑が気になって、意見が言えない、自己主張出来ない、生きにくい世の中です。
特に女性にその傾向が多いのは何故なのでしょう。
様々な脳科学の本を読んで調べてみました。
ローアン・ブリゼンディーン博士*によると、最初は同じ脳を持っている胎児が、受胎後8週目にテストステロン(男性ホルモン)を浴びることで男性と女性を分けるそうです。
テストステロンは勝利をすることや自信、攻撃性や筋肉をつけるのに対し、それを浴びていない女性は情動をつかさどる脳を発達させて、共感力やコミュニケーションを発達させていくそうです。
情動の発達している女性は、周囲が気になり共感力を磨いていきます。
だから、周囲が気になるのは女性の共感力がなせる業、特性なのです。
ではどうしたら、それを乗り越えて自己主張できるようになるのでしょうか。
今回私は、女子大生たちに「健全なジコチューを目指しましょう」と伝えました。
自分の都合や好み、自分に有利に事を運ぶための主張だったら確かにジコチューです。
しかし、組織のために貢献するためのアイデアだったり、自分の信念に基づいた主張だったり、誰かのための発言であったりしたら
その主張をジコチューとは言えないでしょう。
自分が正しいと思うこと、やりたいことは主張しなければ他人任せの人生になってしまいます。
逆に言えば、自分は同意できないと思っていながら他人に嫌われることを恐れて沈黙していたら、もっと良いアイデアを持っているのに提案しなかったら、それはジコチューです。
会議で、責任を取りたくないから発言しないのは、ジコチューです。
実はこの手のジコチューもかなり組織にははびこっていますね。
ジコチューを検索していたら、乃木坂46の「ジコチューで行こう!」という曲を見つけました。
皆に合わせるあけじゃ
生きている意味も価値もないだろう
やりたいことをやれ
ジコチューで行こう!
こんな曲があるというのは、皆分かっているのですね(笑)
(YK)
参考資料 「女性能の特性と行動」~真相心理のメカニズム~ ローアン・プリゼンディーン著*
タグ :DE&Iジコチューテストステロン共感力と女性自己主張
ぶれない発言をしたい
2024年3月8日
 最近、ある人から「川邊さんは男だね」
最近、ある人から「川邊さんは男だね」
と言われました。
「男だ」という表現は若い頃から親しい友人にもたびたび言われたことはあるのですが
それが何を意味するのか分かりません。
しかしそう言われたときは、ポジティブな私は「ビジネスライク」だとか、「合理的に物事考える」とか、「仕事第一」または「決断力がある」「リーダーシップがある」というようなことを言いたいのだろうと、褒められたと捉えるようにしています。
しかし同時に「女らしい」を否定されているようで、落ち着かない気持ちになります。
男性が「君は女だね」と言われたら、どのような気持ちになるのでしょうか。
そもそも女らしい、とか男らしいとか、評価の基準にもならない、誰に対しても意味のない表現です。
しかし私は、そう言われるとただ「よく言われます」と受け流してしまいます。
少し前にあるベテラン政治家が、女性大臣を「おばさんなのに行動力がある」と公の場でコメントしたことが問題になりました。
それを受けて記者会見に出た女性大臣が「ありがたく受け止める」と答えたことが、賛否両論を巻き起こしました。
私だったらなんて答えただろう、と考えてみたのですが恐らく私も「ご厚意ある評価と受け止めます」とか「気にしておりません」とか、受け流して終わりにしてしまっただろうと思います。
が、やはりことはそれだけでは終わりませんでした。
その後すぐに多くの女性政治家や一般女性たちが、「日本の女性大臣がセクハラ発言に抗議しないのは世界に恥ずかしい」、「多くの女性のロールモデルとしての発言ではなかった」と発言をしたベテラン政治家と同じくらい、女性大臣が避難される結果となりました。
その反応を見て、日本の社会はちゃんと着実に成長し続けている、と感じた事件?でした。
自分が日頃、正しいと信じていること、考えていること、思っていること(信念)はどのような状況にあっても、それに従って発言や行動がぶれないようにしたい。
誰もが思っているでしょう。
しかし、同時に私たちは(特に日本人は)、周囲の大切な人に同調したいという思いも強く持っています。
「自分らしくありたい」「自分はユニークでありたい」と思いながら、組織では「皆を喜ばせたい」と同調する。
それが最近起こる組織の問題を引き起こす要因のひとつでもあるのではないでしょうか。
目の前の人を喜ばせるために信念を曲げない、これはかなりハードルの高いことですが今年心がけたいテーマのひとつです。
(YK)
タグ :ウーマノミクス、女性リーダーシップ、女性活躍推進ぶれない女みたい女性政治家男みたい発言のブレ
頭の中の臥薪嘗胆
2023年7月12日
 誰でも人は、多かれ少なかれ、頭の中で自分自身と無言の会話をしています。
誰でも人は、多かれ少なかれ、頭の中で自分自身と無言の会話をしています。
「こうすれば良かった」「今度はああしよう」
それは自分を振り返ったり判断をしたりするときには、役に立つ必要な対話です。
しかし時によっては、それが「内なる批判者」となって自分自身をせめてしまうことがあるようです。
私がよく自分の頭の中でつぶやく言葉がいくつかありますが、それはどれも子供の頃に何かのきっかけで他人に言われたり、
自分が強く影響を受けたりした言葉です。
例えば私の場合、「臥薪嘗胆」という四文字熟語です。
「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」とは将来の成功を期して苦労に耐えること。
高校時代、王貞治元監督似の漢文の先生が、目を見開きすごい熱弁で「中国の時代の武将が薪の上に寝て苦い胆をなめながら再起を誓ったのですよ!」と説明をしてくれた言葉でした。
薪の上に寝たら痛いし、胆を舐めるってどんな味がするんだろう、と私の心に強烈な印象を残して、それ以来、難しいことに出会うと「臥薪嘗胆、臥薪嘗胆」と頭の中で繰り返しています。
漢文の先生には感謝で、この言葉のお陰で私は負けず嫌いになったところもあるのですが、同時に強いプレッシャーになることもあるのは事実です。
あきらめてはいけない、という想いが逆に自分を責めてしまい物事を手放すことが苦手です。
他にも私の頭の中で繰り返す言葉はいろいろありますが、どれもどこかのタイミングで誰かに言われてインプットされた言葉や価値観です。
また誰もが心の中でブレインストーミング(アイデアを出す)をすることはあるでしょう。
自分一人でああでもないこうでもない、ああなったらこうしよう、と仮説を考えて自分と対話することはプラスです。
言葉を持っているからこそできることです。
が、それが「こうなったらどうしよう」「そうなるはずがない」とネガティブな思考を繰り返すとマイナスになります。
こうして考えてみると、心の中の対話は自分自身の自信を獲得するために、上手く使う必要がありそうです。
そして大人になった今、過去に与えられた言葉の扱いとともに、私たちは他人(特に子供や部下に対して)に対して言葉で影響を与えていることに敏感でありたいと思います。
自分も他人もポジティブな言葉で認める。
前向きな言葉をプレゼンとする。
習慣にしていきましょう。
(YK)
参考図書:『Chattaer「頭の中のひとりごと」をコントロールし最良の行動を導くための26の方法』 イーサン・クロス著 東洋経済新報社
関連セミナー「『自信を持たせるフィードフォワード』~女性の活躍を促す~
👇
https://omotenacism.com/seminar/2023/0712/2494/
タグ :ひとりごと女性のコーチング自信を持たせる雅新小胆
 暑すぎる夏でも仕事や勉強は待ってくれない。
暑すぎる夏でも仕事や勉強は待ってくれない。
 会社概要
会社概要 お問い合わせ
お問い合わせ


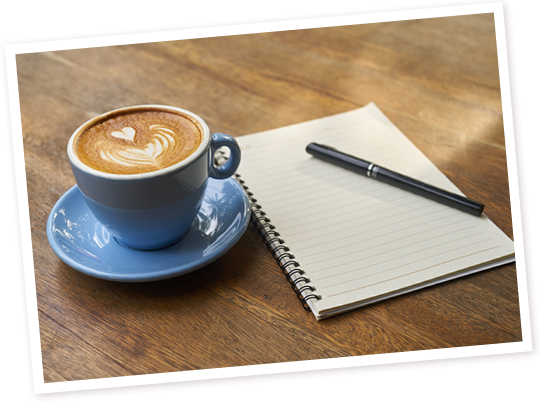

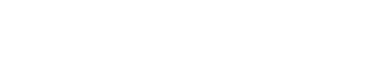 コラム
コラム
 先日、男性の知人に聞かれました。
先日、男性の知人に聞かれました。 相手に共感したり承認したりすることが大切であることは、多くの方が知っているでしょう。
相手に共感したり承認したりすることが大切であることは、多くの方が知っているでしょう。
 違和感を覚えるとき。
違和感を覚えるとき。 このコラムでは男女差を随分扱ってきました。
このコラムでは男女差を随分扱ってきました。 ジコチュー(自己中心)という言葉をとてもよく耳にします。
ジコチュー(自己中心)という言葉をとてもよく耳にします。 最近、ある人から「川邊さんは男だね」
最近、ある人から「川邊さんは男だね」 誰でも人は、多かれ少なかれ、頭の中で自分自身と無言の会話をしています。
誰でも人は、多かれ少なかれ、頭の中で自分自身と無言の会話をしています。